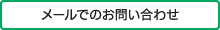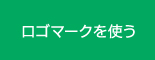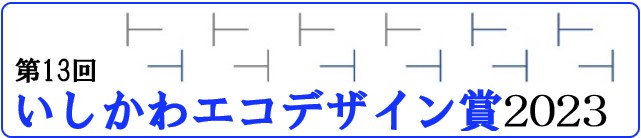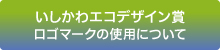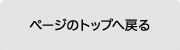- トップ
- よくある問い合わせ
問い合わせ一覧
- Q1
- いしかわエコデザイン賞とはどのような賞でしょうか?
- Q2
- 応募の対象をイメージできません。どのようなものが対象でしょうか?
- Q3
- サービス・建築領域とはどの様なものでしょうか?
- Q4
- 受賞のメリットは?
- Q5
- 今後も継続して募集があるのですか?
- Q6
- Q6. アイデア段階のものや、市場に出せていないものでも応募できますか?
- Q7
- 応募対象者の高等教育機関とは何でしょうか?
- Q8
- ニックネームを記入する場合、匿名で応募可能ということでしょうか?
- Q9
- 審査のポイントは?
- Q10
- 審査項目の「環境への負荷が少ない持続可能な発展が可能な社会への貢献」をどの様に記載したら良いのでしょうか?
- Q11
- 審査項目の「市場性」の将来の実現性について、どの様に記載したら良いのでしょうか?
- Q12
- 応募作品をホームページで公開するとあります。公開を希望しないのですが、問題ないでしょうか?
- Q13
- 応募申込書の別添資料1のA4の1枚紙は様式自由とありますが、どの様なものでもよいのでしょうか?
- Q14
- 応募の際により鮮明な写真や動画等の追加が望ましいと記載がありましたが、必須でしょうか?
- Q15
- プレゼンテーションはどの様なことをするのでしょうか。
- Q16
- プレゼンテーション後に応募申込書の再提出や追加資料の提出をすることもできるとありますが、必要なのでしょうか。
- Q17
- 受賞作品はどのように広報されますか?
- Q18
- アイデア段階、試作段階で応募した製品、サービスを市場に出すための援助や助成はありますか?
- Q19
- 応募に対し、受賞の有無に関わらず、応募された作品について、審査委員会の意見を付される、とありますが、どの様なコメントがあるのでしょうか。
- Q20
- 以前応募して、受賞にいたらなかった作品を再度応募することや、受賞した作品を改善したものを再度応募することは可能でしょうか。
Q1. いしかわエコデザイン賞とはどのような賞でしょうか?
A1. いしかわエコデザイン賞は、カーボンニュートラルの実現(地球温暖化対策)、里山里海保全などの自然共生、資源循環(3R)、環境保全のための情報発信やパートナーシップ(参加・国際的取組)など、持続可能な社会の実現に繋がる、石川発の優れた製品(モノづくり)やサービス・建築(コトおこし)、教育・社会活動(ヒトづくり)を育むことを目的にして、2011年(平成23年)より贈賞しています。
なお、ここでいうデザインには姿・形(意匠・装飾)ばかりでなく、製品やサービスを生みだすコンセプトや姿勢(戦略・企画・設計)などを幅広く含みます。
Q2. 応募の対象をイメージできません。どのようなものが対象でしょうか?
A2. 製品領域の例としては、省エネ製品や温室効果ガス削減につながる製品、風力発電等の再生可能エネルギーに関する製品、さらにエネルギー使用量を削減できる建築物等です。
サービス・建築領域の例としては、地産地消のレストラン、里山活動の情報発信、廃棄物を出さない企業活動、環境に配慮した建築設計等です。
教育・社会活動領域の例としては、先進的な環境学習の実施、温室効果ガス削減に向けた地域活動や学生サークル活動等です。
Q3. サービス・建築領域とはどの様なものでしょうか?
A3. Q2を例とし、製品領域以外の様々な取り組みが該当し、環境に負担をかけない持続可能な社会の実現に向けての戦略や企画、設計を広く指します。過去の受賞作も参考にご覧ください。
Q4. 受賞のメリットは?
A4. エコデザインの第一線で活躍する審査委員による選考を経ての受賞となる、歴史を重ね続けてきた賞です。その表彰を通して、受賞者の取り組みを広くお知らせできるものと考えております。
例年10月頃となる表彰式では、県知事からの表彰状授与、作品の紹介等を行う予定です。
また、「いしかわエコデザイン賞とは」のページにあるとおり、補助金をはじめとした各種の特典があります。
Q5. 今後も継続して募集があるのですか?
A5. 今後とも、毎年の募集を計画しています。
Q6. アイデア段階のものや、市場に出せていないものでも応募できますか?
A6. アイデア段階のものでも応募できますので、学生の方もふるって応募してください。なお、本賞は一般に広く公開することを前提としていることから、応募により公知となることを予めご了承下さい。
また、審査項目で市場性(販売実績(販売見込み)及び対象とするユーザー)や安全性・安心性(生産・供給体制(見込み)及び品質管理)がございますので、アイデア段階や市場に出る予定のものについては、この様な観点での説明、アピールが必要になります。
Q7. 応募対象者の高等教育機関とは何でしょうか?
A7. 本賞では、大学や短期大学、工業やデザインの専門学校または高校の関係者とします。
各種学校や、幼稚園等においては、団体としての応募が可能です。
Q8. ニックネームを記入する場合、匿名で応募可能ということでしょうか?
A8. 特に学生の方に広く応募していただくことを目的に、応募の際にニックネームを付すことも可能としました。
応募製品やサービス、取り組みは本賞ホームページ等で広く公開いたしますが、その際、個人の場合は氏名ではなくニックネームでの掲載を基本とすることを可としています。
しかしながら、賞受賞者は氏名の公開に同意していただく必要がありますので、予めご了承願います。
Q9. 審査のポイントは?
A9. 審査は以下の項目について確認します。
1)環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会への貢献
2)新規性・独自性
3)市場性(販売実績(販売見込み)及び対象とするユーザー(アイデア段階のものについては
実現可能性も考慮))
4)安全性・安心性(生産・提供体制及び品質管理) 等
Q10. 審査項目の「環境への負荷が少ない持続可能な発展が可能な社会への貢献」をどの様に記載したら良いのでしょうか?
A10. 貢献に係る評価値、評価項目の例としては次があります。
・利用段階における温室効果ガスの削減量
・3R(リデュース(Reduce=ごみの発生抑制)、リユース(Reuse=再使用)、
リサイクル(Recycle=再資源化))に関する量
・里山里海の利用・保全活動の生態系への配慮内容
・地域ぐるみの活動や国際的な連携 など
例1:
節電効果が年間138千kWhと試算される。これをCO2削減量に換算すると、76t-CO2/年となる。
(計算:138千kWh/年×0.555t-CO2/千kWh)
例2:
灯油使用量が年間32kL削減されると試算される。これをCO2削減量に換算すると80t-CO2/年となる。
(計算:32kL/年×2.49t-CO2/kL)
例3:
ごみの発生量を年間○t削減できると試算される。
例4:
里山の保全活動により、ホタルが生息するようになった。ホタル見学ツアーに年間○人参加してもらえるようになった。
例5:
○○国の△△市と環境保全活動の情報交換、人事交流を□年間行っている。
注意:
1)上記例は一例であり、応募者が考えるエコアピールを記載してください。
2)CO2削減量など客観的、定量的評価がある場合にはより説得力があります。
3)CO2削減量算出方法については、公益社団法人 いしかわ環境パートナーシップ県民会でも相談を受け付けています。
Q11. 審査項目の「市場性」の将来の実現性について、どの様に記載したら良いのでしょうか?
A11. 現在、市場にあるものは、販売実績やサービスの実績を記載するとともに、今後の見込みについて記載して下さい。
市場に出る前のものについては、実現までの想定される計画(ロードマップ)や課題について記載して下さい。
Q12. 応募作品をホームページで公開するとあります。公開を希望しないのですが、問題ないでしょうか?
A12. 特に学生の方に広く応募していただくことを目的に、応募の際にニックネームを付すことも可能としておりますので、ホームページでの公開にご協力をお願いします。
また、一次審査は応募書類等の内容で審査を行いますが、二次審査では県民投票も予定しています。あわせて、必要に応じて応募者に申請書類の内容等についてヒアリングを実施することがあります。
どうしても公開に同意いただけない場合には、受賞を辞退いただく場合がございますのでご了承願います。
Q13. 応募申込書の別添資料1のA4の1枚紙は様式自由とありますが、どの様なものでもよいのでしょうか?
A13. 製品領域の応募であれば製品広告リーフレット、サービス・建築領域であれば、取り組み全体をイメージできるものを記載し、写真やイラスト等を活用して積極的な説明(PR)の内容にして下さい。また、企業・団体名、連絡先等も入れて下さい。
この別添資料1は審査委員が審査において製品、サービス・建築の特長などを把握するために使用させていただくものですので重要な資料です。
選考過程に加えて、本賞授賞式等での展示、受賞製品、サービス・建築を一覧にした印刷物の原稿等に使用します。このため、多くの方に分かりやすいものとしていただくことが好ましいです。
Q14. 応募の際により鮮明な写真や動画等の追加が望ましいと記載がありましたが、必須でしょうか?
A14. 一次審査は主として別添資料1のA4の1枚紙を使用します。
しかしながら、製品領域であればより鮮明な写真やパンフレットが添付されていた方が好ましいと思われます。
また、サービス・建築領域については、イメージ図やサービス内容を記録した動画があればより具体的なアピールが可能です。
なお、添付いただきました写真や動画を記録した記録媒体(CD-RやDVD-R等)などは返却できませんのでご注意願います。
Q15. プレゼンテーションはどの様なことをするのでしょうか。
A15. 一次の書類審査通過者の方には審査委員の方々に、応募作品についてご紹介いただきます。開催日時、発表時間、発表方法などの詳細は審査通過者の方に直接ご連絡いたします。
Q16. プレゼンテーション後に応募申込書の再提出や追加資料の提出をすることもできるとありますが、必要なのでしょうか。
A16. 応募者が、プレゼンテーションの場などでの審査員との意見交換から、より重点的に説明(PR)した方が良いと考えられることもありますので、応募申込書の再提出や追加資料の提出を可としています。
最終審査は、これらの書類やプレゼンテーションの発表より非公開で審査します。
Q17. 受賞作品はどのように広報されますか?
A17. いしかわエコデザイン賞の表彰状を石川県知事より渡す予定としております。
また、受賞作品を一覧にした印刷物を作成するとともホームページ等で広くお知らせすることとしています。
なお、選考過程についても、一般投票や県民WEB投票も行う過程を通じ、作品を広くお知らせする機会になると考えています。
Q18. アイデア段階、試作段階で応募した製品、サービスを市場に出すための援助や助成はありますか?
A18. 改良、販売促進、活動等に係る大賞受賞者への補助金のほか、大賞・金賞受賞者ともに、製品等の改良、販路開拓等について、各領域の専門家による助言指導を受けることができます(直接訪問1回を予定)
Q19. 応募に対し、受賞の有無に関わらず、応募された作品について、審査委員会の意見を付される、とありますが、どの様なコメントがあるのでしょうか。
A19. 受賞作品はどの様な点を評価したのか、今後に期待される事柄などのコメントを公開します。残念ながら受賞にいたらなかった応募者に対しては、より改善を望む点や望ましい方向性についてコメントさせていただきます。
Q20. 以前応募して、受賞にいたらなかった作品を再度応募することや、受賞した作品を改善したものを再度応募することは可能でしょうか。
A20. 以前応募して受賞にいたらなかった作品を、審査員の意見などを参考に、より良いものとされていれば応募は可能です。改善されたポイントを明確にご説明いただくと分かりやすいかと思います。
また、いしかわエコデザイン賞は受賞年によって区分されますので、受賞作品を改善したものを再度応募することも可能です。持続可能な社会に向けてより良く改善をされている作品を応援させていただきたいと思います。
石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
TEL 076-225-1469 FAX 076-225-1479
E-mail:cn2@pref.ishikawa.lg.jp