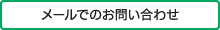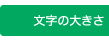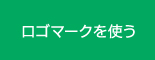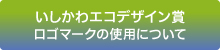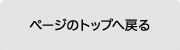- トップ
- 第8回 いしかわエコデザイン賞 2018 応募製品・サービス
平成30年8月26日(日)10時から「いしかわ環境フェア2018」内のステージにて、公開プレゼンテーションを実施します。
■ 応募製品・サービスの紹介
書類による一次審査を通過した応募製品・サービスの紹介ポスターとアピールポイントを掲載しています。
紹介ポスターは、表示に時間がかかる場合があります。
| 領域 | 応募製品・サービス名 | 応募者 | 状況 |
|---|---|---|---|
| アピールポイント | |||
| 製品 1 |
株式会社アシストエリア | 発売済 2018年3月 |
|
| ATTE chouchou(アッテ・シュシュ)は従来の靴用消臭グッズのイメージを払拭し、消臭効果があるだけでなくインテリアとしても機能します。本体は捨てられている資源をリサイクルするというコンセプトを基に独自技術で間伐材・廃材となった能登ヒバモルダーチップを配合した再生紙商品です。能登ヒバの消臭性を活かしたエコロジーなキットはスタンド部分も含めB5平面体から立体形状のフォルムへと安全に組立てられます。「山と歩く」、「古都の美」シリーズの8種類のラインナップは石川の雄大な自然や金沢の伝統とモダンを描き、イラストやコメントをユーザーが自由に書けるプレーンタイプも備え、新たなコミュニケーションツールとしても期待できます。この商品は再生紙を利用した持続可能なモノづくりの挑戦の一歩でもあり、靴の臭いの解消と日常生活に彩りを添えるデザインとしました。 |
|||
| 製品 2 |
石川樹脂工業株式会社 | 発売済 2016年5月 |
|
| 楽しいパーティーで食器が割れてしまって興ざめ。そんな経験ありませんか?使い捨てのプラスチックを廃棄するときの罪悪感ありませんか? 新素材トライタンを採用した“Plakira”なら車が踏んでも割れず、透明感を保ったまま永く使える食器です。金沢のデザイナーsecca incと共同開発した皆さんに安心して、日常生活に溶け込んでずっと使い続けられる商品です。 |
|||
| 製品 3 |
株式会社エコシステム | 発売済 2018年2月 |
|
| 当社は廃瓦をリサイクルしている会社です。廃瓦は粉砕され、舗装材として生まれ変わります。その舗装材の製造プラントを紹介します。 廃瓦は国内で年間100万t 弱程排出され、埋立処分場の逼迫原因の一つとされています。しかし瓦は多孔質な物質であり、舗装材とすることで保水性が高い、ヒートアイランド抑制に効果的なエコ舗装材となります。埋立処分場の負荷軽減と、エコ性能のある瓦舗装材の提供という瓦リサイクル事業を全国19社でネットワークを形成し、地産地消で行っています。 瓦舗装材を製造する際、従来は固定式のプラントか現場でタライミキサー等で製造して施工していました。しかし高効率な何でも練れる固定式のプラントはあまりなく、タライミキサーでの製造だと非常に大変で、その結果リサイクルがそれほど進みませんでした。 その現状を打破させるべく、車載式瓦舗装材プラントを開発しました。これから国内外に展開させる事を考えています。 |
|||
| 製品 4 |
合同会社山立会 | 発売済 2017年12月 |
|
| 日本初!イノシシ脂30%配合ハンドクリーム。 イノシシの食肉処理の過程で、これまで廃棄していた“腹脂”を有効活用したハンドクリーム「INO」を開発しました。手荒れなどのダメージに効果があると里山で使用されてきたイノシシの脂。肌を柔らかく滑らかにし、潤いを保ちます。また、白山麓の間伐材を利用して作られたクロモジの天然香料を使用し、いやし効果が期待できます。 新たな里山資源を活用しながら、里山の魅力を発信していきたい。 |
|||
| 製品 5 |
株式会社白山機工 | 試作段階 2019年1月発売 |
|
| 社会問題化している「宅配便の再配達」。年間9万人相当の労働力が再配達に費やされ、再配達のトラックからは年間42万トンものCO2が排出されています。 その抑止策として期待されるのが「宅配ボックス」です。当社は1995年から宅配ボックスの製造を手掛けていますが、問題解決をさらに後押しすべく、宅配ボックスの製造技術とIoT技術を融合した「店舗受取型IoTロッカー」の開発を進めています。 自宅に設置する宅配ボックスとは異なり、本製品は小売店の店頭に設置するロッカーです。「昼休みに注文しておいた店舗商品を、仕事帰りにロッカーで受け取る」というサービスを想定しており、店舗営業が終了した夜中でも受取りが可能になります。 この製品は、「注文した商品を自ら取りに行く」という消費者行動を促し、「再配達を減らす」のではなく「配達自体をなくす」というアプローチで環境負荷の軽減を狙ったものです。 |
|||
| 製品 6 |
鳥居醤油店 | 発売済 2018年3月 |
|
| 当社では、能登産の大豆と小麦、塩を原材料に、明治時代建造の蔵の中で、昔ながらの方法で、手間ひまかけて、手作りの醤油をつくっています。杉桶で2年間天然熟成した醤油が当社の主力商品ですが、醤油を仕込んだ際に出る大量の「もろみ」の搾りかす(=「もろみかす」)は、今まで廃棄処分されていました。 醤油屋の食卓では、その「もろみかす」を漬物床にしたり、お肉に漬けたりと利用していますが、大量に出る「もろみかす」のほんの一部に過ぎませんでした。「もろみ」自体全て厳選した原材料からできたもので、「もろみかす」を捨ててしまうことは非常にもったいないという思いを持っていました。 その「もろみかす」を利用し、醤油屋の思いを伝える商品をつくろうということで完成したのが、この『もろみシリーズ』です。「もろみかす」を乾燥させて粉砕した『もろみ粉』、そのもろみ粉を珠洲産の塩とブレンドした『もろみ塩』を少量の瓶にパッケージすることで、暮らしに「もろみ」を取り入れてもらえることを意図し、廃棄するところのない商品づくりを目指しています。 |
|||
| 製品 7 |
ガレリア画廊 | 発売済 2018年2月 |
|
| 砂糖のかわりに白山麓で昔から作られてきた「米飴」を復活させ、これを牛乳と混ぜて、「ゴハンみたいなアイス」を手づくりしています。 材料は、やまだ農場(白山市)の「うるち米」、わくわく手づくりファーム(川北町)の「麦芽」、松任地域産の「おまっと牛乳」と、全てを手取川流域の地産品のみにこだわり、人工の添加物は一切使っていません。一升の米から4リットル程度しか作れない希少なアイスです。 米は精米時に割れた市場に出回らないものを地元農家から直接仕入れることで食材の有効活用につながり、麦芽や牛乳も地元のものを厳選しているため輸送コストを低減しています。また、地元の障害者支援施設に製造・包装を外注する等、地域のネットワークを活かして、地域の雇用にも貢献していきたい。 |
|||
| サービス 1 |
インプロノート | 提供済 2016年9月 |
|
| 地元の農家と共に試みる里山の保全、循環に向けた新しい取り組み。里山の保全ではなく、これに直接関わる地元の農家の取り組みであることを強調したい。 決して好条件とは言えない里山での農業において、農家に負担のかからない形で環境保全を持続させるために数年前から開始。化学肥料と農薬を使用せずに里山の保全、生物多様性の維持を目指すが手作業中心の農業に回帰するのではなく、現代の技術、農機具を使った農作業とすり合わせる。また農産物についても従来の品種ではなく雑草や病気に強い古代種を選定するなど既存の栽培体系に縛られないようにしている。資材については農家が米や大豆を収穫する際に出てくるもみ殻、米ぬか、鞘などをペレット化にする。ペレット化にすることで農機での散布が可能となる。 環境にやさしい農作物や肥料の地産地消を繰り返すことで化学肥料や農薬を使わないで持続性のある里山の環境保全を目指す。 |
|||
| サービス 2 |
リクル | 提供済 2017年1月 |
|
| 使用を終えた制服(体操服・学用品・ランドセル)を有効活用するための制服リユース店です。母親同士のつながりが少なくなり減ってしまったおさがりの習慣が、「リクル」を通すことで、より大きなおさがりの輪となるように活動しています。制服のリユース(再使用)は、同じ地域のみんなで助け合えるシステムです。 「もったいない」という気持ちを多くの人に持ってもらい、おさがりを地域のみんなで回すことで、今まで捨てられていた制服を有効活用できるため、エコにつながります。譲り受けた商品は、点検・補修・クリーニングをして、定価の約3割という低価格にて販売をしています。そのままではリユースできない傷みのある制服や、モデルチェンジをした制服から部品を取り、補修の材料としても活用しています。 今後は、バッグや小物などのリメイク品を作成・販売していきたいと考えています。 |
|||
| サービス 3 |
合同会社のとしし団 | 提供済 2015年11月 |
|
| これまで田畑を守るために捕獲したイノシシは廃棄していましたが、貴重な資源として活用を図ることで、私たちとイノシシが共存できないかという思いから、2015年に「のとしし大作戦」として事業を開始しました。里山に住むイノシシに罪はありませんが、能登の地で伝統や文化を守りながら暮らしていくために、また新しく農業を始めたいという希望をもった方のために、イノシシを獣害から特産品へと転換する挑戦です。 ジビエ肉として、安全で安心な食肉を生産し、野生の味を楽しんでもらうことはもちろんですが、このプロジェクトでは、廃棄物として処分されることの多い皮、骨、内臓についても、特産化の試みを始めています。いのちの営みに感謝しつつ、貴重な資源として余すことなく活用していくことを目指しています。 |
|||
| サービス 4 |
IM普及協議会 〔北菱電興(株)、(株)別川製作所、石川県立大学〕 | 提供済 2017年1月 |
|
| 白山市上野町地内において、大日川を水源とした農業用水の排水を利用し、水車発電により約6.0kW程度の電力を得ています。水車で発電した電気は、イチゴ栽培ハウスの動力電源として、夏季のエアコン設備、冬季の暖房設備、温水生成設備、融雪設備等に利用され、化石燃料に頼らない持続可能なエネルギー供給システムを実現しています。 イチゴ栽培ハウスは耕作放棄地を再生利用しており、イチゴ摘み取り体験等を通じて交流人口が増加したことから、観光資源として一役買っています。また高品質イチゴの栽培を通し、魅力ある地域ブランドを築く事で、新しい雇用を生み出す可能性も考えられます。 水力発電・イチゴ栽培の技術開発では、石川県立大学及び金沢工業大学と共同研究を行い、現在も研究題材として本フィールドを活用しています。また、地元の農業組合法人とイチゴ栽培を共同で運営する事で、地元の方々のコミュニティーの場所として活用されています。 |
|||
| サービス 5 |
NPO法人白山高山植物研究会 | 提供済 2013年6月 |
|
| 1998年から白峰で始まった白山の高山植物の低地栽培。地球温暖化をはじめとする自然環境の変化から高山植物を守るため、生息地外の保護増殖事業として国内において先進的役割を果たしてきました。 その過程で、栽培が成功し増殖された高山植物を、過去に人為改変され、荒廃し、ハゲ山となった放棄地で試験的に植栽しました。多くの人たちの協力と努力のもと、今では約50種類10万株以上の白山の高山植物が咲き乱れる「お花畑」に生まれ変わりました。 毎年、高山植物が一斉に花開く6~7月には、その光景を見ようと県内外から多くの人々が訪れるようになりました。当研究会の取り組みは、環境保護のみならず観光振興、自然教育で大きな波及効果を生み始めています。 また、白山の高山植物を保全する先駆的な試みは、全国に水平展開することで、日本全国の高山植物の保護にもつながります。 |
|||
| サービス 6 |
加賀木材株式会社 | 提供済 2017年3月 |
|
| 2011年6月、「能登の里山里海」は日本で初めて世界農業遺産に認定されました。能登の里山里海を守るためには、山から流れるミネラルを多く含んだ良質な水が必要ですし、森林はCO2も吸収して地球温暖化も防ぎます。その生産工場は健全な森林です。その森林がいま、高齢化や輸入木材等におされ、伐採されず、植林もされず、荒廃してきています。これは加賀地区でも同様で石川県全体の大きな問題です。原因は丸太の買取価格が安く、流通に出しても赤字になるからで、林業従事者の生活が成り立たない状況です。 このプロジェクトでは、2016年7月、弊社が能登中核工業団地(志賀町)に新設した「のと里山工場」(敷地15,000m2)において、 ① 建築用の安価な木材に特殊加工を施し、高付加価値商品に変える ② 丸太加工の工程で出る端材等約4割をタダ同然で処分している部分を高付加価値商品に変える ③ ①と②で出る利益により、丸太の買取価格を健全な値段にするとともに基金を設立して、林業に還元する ④ 高収益な産業にできれば、林業が活性化し、健全な森林のサイクルが作られる ⑤ 県産の能登ヒバやスギ等の木の良さを知ってもらう施設をつくり、林業の重要性の啓蒙活動を行う ことにより、「山への恩返し」を見える形で取り組んでいます。 |
|||
| サービス 7 |
株式会社サンライフ/ 有限会社あさひ農園 |
提供済 2016年 |
|
| 地域循環圏とは、地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、それが困難なものについては循環する環を広域化し、重層的な地域循環を構築するという考え方であり、地域特性に応じて、最適な規模の循環を形成する必要があります。 当社は、能登町の里山里海地域において、食品スーパー、養鶏、食品製造、産業廃棄物処理、建設業、農業、堆肥製造、天然塩製造などを手掛けていますが、地域レベルで資源を無駄なく有効に活用する取り組みを行っています。能登の地で循環型の多角経営を進めることで、雇用の創出、地域の活性化に寄与していきたいです。 |
|||
※「アピールポイント」の記載は応募申込書の内容を転記したものであり、事務局は内容の適正を確認しておりません。
問い合わせ先
公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議
石川県生活環境部温暖化・里山対策室
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
TEL 076-225-1462 FAX 076-225-1479 E-mail:ontai@pref.ishikawa.lg.jp
公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議
(県民エコステーション)
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目1番地
TEL 076-266-0881 FAX 076-266-0882 E-mail:info@eco-partner.net