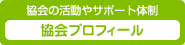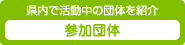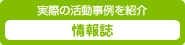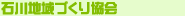
�����ǁF�ΐ쌧���U�����n��U���ۓ�
��920-8580
�ΐ쌧����s�ƌ�1-1
TEL:076-225-1335
FAX:076-225-1328
�y���������n��Â���~�w2025�v�̊J�Âɂ��āz
���n��Â���~�w�Ƃ́H��
�@�ΐ�n��Â��苦����N�J�Â��Ă���A�n��Â���V���|�W�E���ł��B
�@�W�܂��ĉ~�w���͂ނ��Ƃ��A�n��Â���̌����́i�G���W���j�ɂȂ�܂��B
�����N�x�̃e�[�}��
�@�u�l�Â���E�ւ��Â���v
�@�`�W�l���������炷�V���Ȓn��Â���̎��H�`
�@�n��Â���̌���ł́A�����l�������ɂ��A��p�҂�S����̊m�ۂ��i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�����炽�߂Ēn��̖��͂⊈���������鉻���A�����O����W�l�����Ăэ��݁A�Ƃ��ɂȂ��邱�ƂŎ����I�ɉ����ł�����@���l���Ă݂܂��B
�@��u����Q���ғ��m�̈ӌ�������ʂ��āA�ۑ��^��m�ɂ��A���̃X�e�b�v�����L���܂��傤�B
���J�������@
�@�ߘa7�N11��2���i���j13:00�`18�F00�i��t�J�n12:30�`�j
�@��������10�F00����u�n��Â��芈���̑̌���v���J�Â��܂��B
���Q���ɂ������ā�
�@�ȉ����Q�Ƃ̂����A���\���݂��������B
�@��W���100��
�@����ɒB������A���ߐ�܂��B
����ꁄ
�@�\���s�C��������ٌ𗬃z�[���ق�
�@�i�\���s�C�����k10�Ԓn�j
�@
���Q���Ώہ�
�@�n��Â���ɋ����̂���E�S�̂�����Ȃ�A�ǂȂ��ł��Q���\�ł��B
���Q���
�@����
�@���𗬉�̂ݎQ����2,000�~�ƂȂ�܂��B
���Q���\���݁�
�@10��24���i���j�܂łɂ�������\���t�H�[�����炨�\���݂��������B
�@�ΐ�n��Â��苦����ǂ��ĂɃ��[���E�e�`�w�ł���t���܂��B
�@�\���݂̍ۂ́A�����O�E�����c�́E�d�b�ԍ��E�Q�����@�E�Q���v���O���������`�����������B
�@���ꕔ�v���O�����݂̂̎Q�����\�ł��B
���\���݁E�⍇�킹�恄
�@�ΐ�n��Â��苦����ǁi�ΐ쌧���U�����n��U���ۓ��j�S���F�R�c
�@TEL�F076-225-1335
�@FAX�F076-225-1328
�@MAIL�Fchiiki1@pref.ishikawa.lg.jp
���v���O������
�@���ڍׂɂ��ẮA�`���V���������������B
�@10:00�`
�@�n��Â��芈���̑̌���
�@�@�P�@�}�E���e���o�C�N�̑�햡
�@�@�@�@�@�Љ�c�́F�C�[�X�^���g���C��MTB�N���u
�@�@�Q�@���L���ȕ\���̐S�ƋZ�p
�@�@�@�@�@�Љ�c�́F�^���g�����w�Z
�@�@�R�@�\���̗��R���u���E�[�߂�E�������v
�@�@�@�@�@�Љ�c�́F�\���̗��R�t�@����y��
�@13:00�`
�@�@�J��
�@�@�@��Î҈��A
�@�@�@�I���G���e�[�V����
�@13:15�`
�@�@��u��
�@�@�@�e�[�}�u�n��Â���̐V�������ԁE�W�l���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�`�����\�Ȓn���ڎw���ā`
�@�@�@ �u�t�F���v���c�@�l�ӂ邳�Ɠ�����Z���c
�@�@�@�@�@�@�@�n�抈���x���ۉے��@���@���I�q�@��
�@�@�@�@�@�@�@�n�抈���x���ێ�C�厖�@�c粁@���@��
�@14:30�`
�@�@�O���[�v�Z�b�V����
�@�@�@�O���[�v�ɕ�����āA��u���̓��e�ɂ��Ĉӌ��������܂��B
�@
�@15:40�`
�@�@�g�[�N�Z�b�V�����^�S�̉�
�@�@�@�e�O���[�v����o���ꂽ�ӌ��⎿������グ�Ă����܂��B
�@�@�@�n��Â��芈���̑̌���╁�i�̊����̊��z����A�W�l�����ƒn�摤�𗝉�
�@�@�@���Ȃ��痼�҂��Ȃ��A�����\�Ȋ�����ڎw�����Ƃ����L���܂��B
�@17:00�`
�@�@�𗬉�
�@�@�@�y�H���y���݂Ȃ��獧�e��B
�@�@�@���Q����F2,000�~�i�����W���j
�@18�F00�`
�@�@��

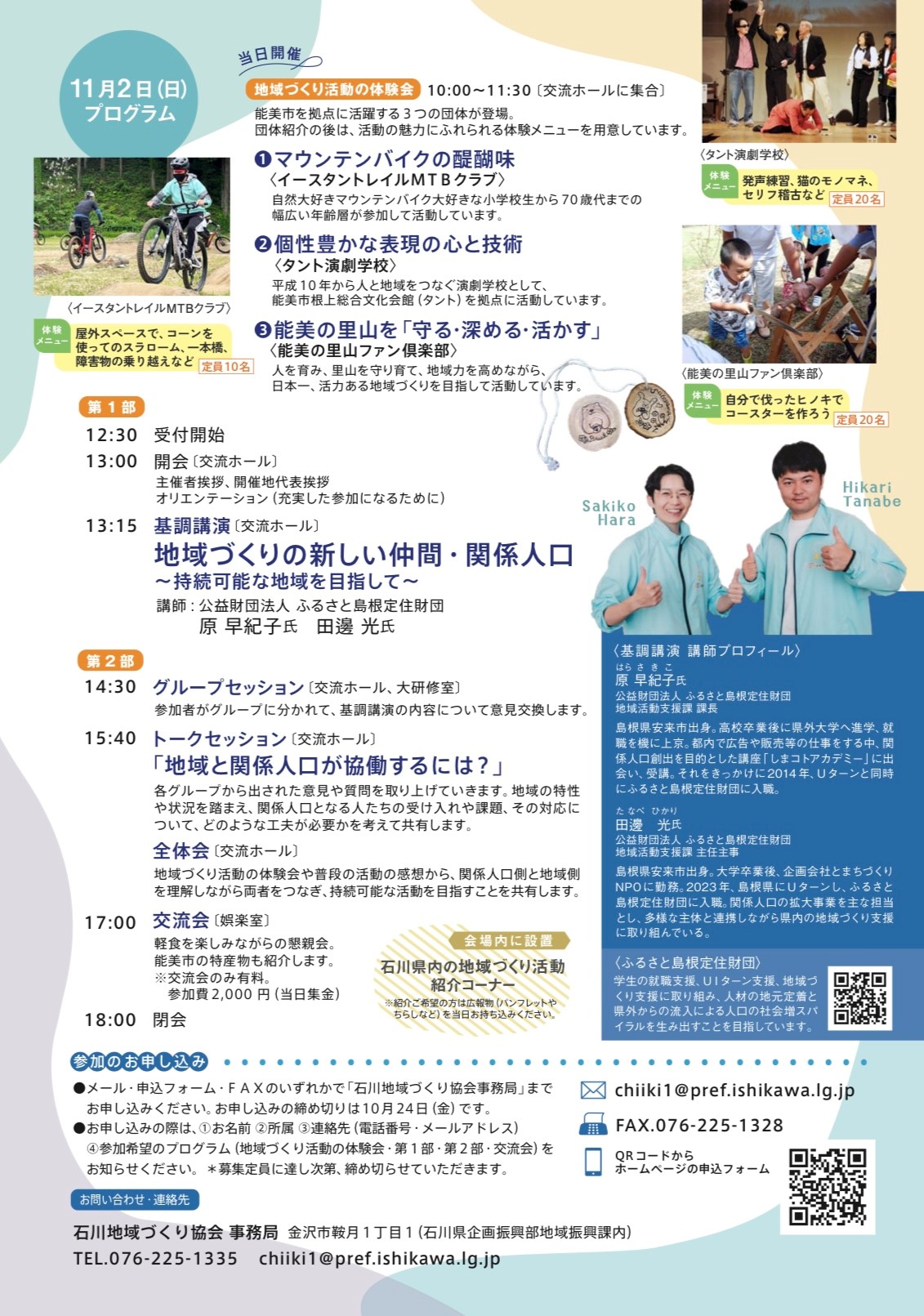
�@
��2024�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
��2023�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
��2022�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
��2021�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
�@�@�@
��2020�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
��2019�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
��2018�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
��2017�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
��2016�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
��2015�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
��2012�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
�@ �P.��P���ȉ���PDF
�@ �Q.��Q���ȉ���PDF
�@ �R.��R���ȉ���PDF
�@ �S.��S���ȉ���PDF
�@ �T.�S�̉�E�ЂȒd�g�[�N�@��PDF
�@ �U.�S�̉�E�ЂȒd�g�[�N�A��PDF
��2011�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
�@ �P.��P���ȉ���PDF
�@ �Q.��Q���ȉ���PDF
�@ �R.��R���ȉ���PDF
�@ �S.��S���ȉ���PDF
�@ �T.��T���ȉ���PDF
��2010�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
�@ �P.�\���E���}�̃��b�Z�[�W�A�n��Â���\����PDF
�@ �Q.��P���ȉ���PDF
�@ �R.��Q���ȉ���PDF
�@ �S.��R���ȉ���PDF
�@ �T.��S���ȉ���PDF
�@ �U.��T���ȉ���PDF
�@ �V.�S�̉�A�S�̃A���P�[�g�A�𗬉�@��PDF
��2009�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
�@ �P.�\���E���}�̃��b�Z�[�W��PDF
�@ �Q.�n�����\����PDF
�@ �R.���ȉ�ڎ���PDF
�@ �S.��P���ȉ���PDF
�@ �T.��Q���ȉ���PDF
�@ �U.��R���ȉ���PDF
�@ �V.��S���ȉ���PDF
�@ �W.��T���ȉ���PDF
�@ �X.�S�̉�A�ЂȒd�g�[�N��PDF
�@ 10.�S�̃A���P�[�g�A�𗬉���PDF
��2008�N�x�̎��{����PDF�ł������������܂�
�@ �P.�\���E���}�̃��b�Z�[�W��PDF
�@�@�Q.�ڎ��A��P���ȉ���PDF
�@ �R.��Q���ȉ���PDF
�@ �S.��R���ȉ���PDF
�@ �T.��S���ȉ���PDF
�@ �U.��T���ȉ���PDF
�@ �V.�S�̉�A�p�l���f�B�X�J�b�V������PDF
�@ �W.�S�̃A���P�[�g�A�𗬉���PDF
�@ �X.�S�̉�A�ЂȒd�g�[�N��PDF
�@ 10.�S�̃A���P�[�g�A�𗬉���PDF