開業効果を最大限に引き出し、県内全域に波及させるには、交流人口拡大の中核を担う観光の推進、多くの訪問者を受け入れるための交流基盤整備、地場産業の振興につなげるための地域経済競争力の強化が必要な要素と考えています。そこで「STEP21」では、
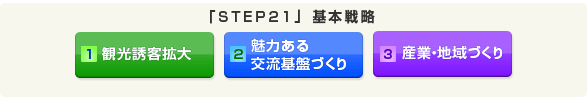
の3つを「基本戦略」に設定し、さらにこれらを施策分野ごとに11の「戦略の方向性」に区分、38の「施策の柱」に細分化して、今後取り組んでいく具体的な施策や事業などを提示しています。
![[基本戦略1] 観光誘客拡大](img/strategy1-ttl.gif)
人口減少時代を迎えた今日、交流人口の拡大により地域の活性化を図ることが大きなテーマであり、交流人口拡大の中核を担う観光に大きな役割が期待されています。
このことから4千万人を超える人口を擁する首都圏と本県を直結する北陸新幹線の開業は、観光誘客の絶好の機会であり、開業を見据えて、本県の豊かな観光資源に一層の磨きをかける一方、訪れる人に満足して頂くホスピタリティの醸成を進めるとともに、首都圏に対して戦略的な情報発信を行い、交流人口の拡大を図ることが必要です。
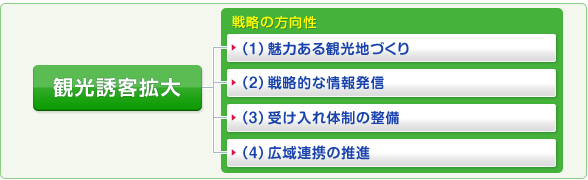
温泉地の再生や既存の観光資源の活性化と新たな観光資源の発掘を進めるとともに、地域に伝わる祭りや伝統芸能等を活用しながら地域住民とのふれあいが楽しめる魅力ある観光地づくりを推進します。

個性ある温泉地づくり(多様な宿泊形態への対応など)
街並み景観の向上と歩行空間を確保し、楽しみながらまちなかの移動ができる回遊ルートづく り(都市ルネッサンス石川・都心軸整備事業など)
商店街とタイアップした観光イベント等の開催
キリコ体験、地引網体験、塩づくり体験、和菓子づくりなど多彩な体験メニューの創出

お旅まつりや青柏祭、 キリコ祭り等の旅行商品化
石川の海岸線約580kmをきれいにする海岸愛護運動「クリーンビーチ」
民間企業による植樹活動(企業の社会貢献活動)
観光客のニーズや女性、団塊世代など性別、年代別の嗜好を踏まえ、インターネットや雑誌などの情報ツールを活用して戦略的な情報発信を行うとともに、北陸新幹線開業前後にJR各社とタイアップして大型キャンペーン等を展開します。
メディア、インターネット等を活用した効果的な情報発信(メディアとのタイアップ企画、キャンペーン活動の推進、ミシュランやブルーガイドの評価を活用した情報発信)
首都圏の県関係者と連携したPRの推進
北陸新幹線に相応しい列車のネーミング

「加賀・能登・金沢 江戸本店」(有楽町)の機能充実
首都圏のコンビニエンスストアなどとの連携
(石川の農林水産品を使った商品の販売など)
市町、観光団体等と連携した北陸新幹線金沢開業前後の大型キャンペーンの展開
開業に合わせ、魅力あるイベント等の検討
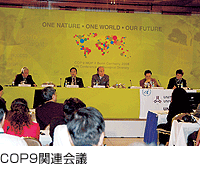
MICE市場の動向に対応した各種学会等補助金の充実
大学・研究機関等との連携による誘致促進

海外メディア(台湾、韓国、豪州等)招へい事業等による本県魅力の発信
観光地での案内看板等の各言語対応の充実
※1 デスティネーションキャンペーンとは、全国のJRが毎年4回実施するキャンペーン。JRと地方自治体、旅行代理店、観光事業者等が連携して様々な取組みを行う。期間は通常3カ月間。
※2 MICEとは、Meeting(会議・研修・セミナー)、Incentive tour(報奨・招待旅行)、Convention/Conference(大会、学会、国際会議)、Event/Exhibition(イベント、展示会)。
県民一人ひとりが心をこめて観光客をお迎えする「おもてなしの心」の醸成を図ります。
地域の観光素材を「お国自慢」として県内外へ情報発信
広く県民を対象とした「おもてなし講座」の開催

観光従事者等のスキルアップ(観光案内できる乗務員の育成、ご当地検定の活用など)
観光ボランティアガイドの育成(ほっと石川観光ボランティアガイド連絡協議会による研修の実施など)

各種案内板のデザインの統一性の確保
わかりやすい案内板の整備
広域的な周遊観光に対応するため、中部9県、北陸3県、北陸新幹線沿線地域とも連携した情報発信により観光誘客を促進します。


能登空港、小松空港及び富山空港との連携による広域観光のPR
広域周遊ルート商品の開発(旅行会社への働きかけ)
観光情報の相互発信等による共同キャンペーンの展開
北陸新幹線沿線都市観光推進会議の開催
![[基本戦略2] 魅力ある交流基盤づくり](img/strategy2-ttl.gif)
首都圏から大量のビジターを受け入れるには、道路や港湾、空港といった交流基盤の整備・充実に加え、これらのハードを活用するソフトが重要となってくることから、ビジターの回遊を促すコリドー(回廊)の形成というコンセプトに基づき、案内情報、乗り継ぎの利便性向上といった二次交通の充実などに力を入れるとともに、地域固有の資源に磨きをかけ、ビジターを迎え入れる交流拠点づくりや若者を呼び込めるにぎわいのあるまちづくりに取り組む必要があります。
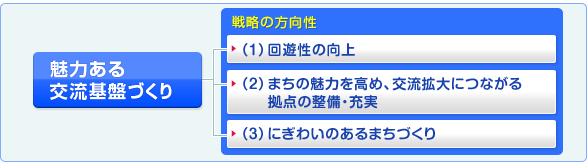
温泉や食、歴史・景観、伝統文化など地域固有の資源に磨きをかけるとともに、これらの資源を結び付けたコリドー(回廊)の形成を図ることが重要です。このためには、道路など交流基盤の整備とともに、目的地へ至るプロセスを楽しめるようなソフトの充実(仕掛けづくり)が不可欠です。

交通事業者、観光事業者、行政等による連絡会議を設け、二次交通充実に向けた取組みを促進
白山IC(仮称)の整備促進
南加賀道路の整備促進
能越自動車道の建設促進(輪島道路・七尾氷見道路の整備促進、田鶴浜〜七尾間の早期ルート決定)など

県内の各道の駅が取り扱う特産品の情報発信及び販売拡大
いしかわ風景街道(シーニック・バイウェイ※1)の整備促進
※1 シーニック・バイウェイとは、「風景の良い道路」の意味で、沿道景観を楽しみながら、自然・歴史・文化などを体験できる施設を巡る観光ルート
ビジターを二度、三度と招くには、常に新しい魅力を創り出し、 新たな人の交流を生み出していくための努力が必要です。観光地としての魅力づくりに加え、本県の大きな特性である先人が築き上げてきた歴史や伝統文化の保存・継承・活用などの取組みを通じ地域全体の価値を保全することが集客にもつながります。
石川・金沢らしい新幹線駅舎の整備
金沢城公園の整備、本多の森公園の整備
市街地再開発事業の推進(金沢駅武蔵地区など)
まちなかで歩行者優先、安全・安心で楽しみながら回遊できる歩行環境の整備を推進(まちなか歩行回廊の整備[ルート設定、案内サインの整備など])

無電柱化を核とし た総合的な街並み 景観の向上
沿道の景観形成と緑化の推進
住民参画による地域の特色を生かした個性的な街並みづくりの推進(各市町の取組みを支援)
町家の継承と利用活性化

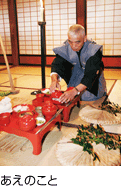
尊經閣文庫分館の情報発信や展示の充実
御願神事(竹割祭り)や青柏祭、あえのことなど無形民俗文化財の保存・活用

車が通れる海岸として全国的に有名な千里浜海岸の保全
里山里海の利用・保全(生物多様性に配慮した農地整備のモデル実施など)
自らの地域社会や都市を愛し、誇りをもち、楽しく幸せに暮らしているならば、自ずとだれしもがその地を訪れたくなるものです。住んでよし、訪れてよしの視点に立ったにぎわいのあるまちづくりを進めます。

街並み景観の向上と歩行空間を確保し、楽しみながらまちなかの移動ができる回遊ルートづくり(再掲)(街なか再生・目抜き通り整備事業など)
並行在来線の安定的な経営・運行
交通事業者等が行う鉄道駅・バス停のバリアフリー化等の設備整備に対して支援
自転車利用環境の向上(観光用駐輪場の整備、レンタサイクルの返却場所の複数化)
宿泊・観光施設等において、より快適にインターネットを利用できる環境の整備促進
携帯電話情報サイトによる観光情報や交通アクセス情報等の提供促進
![[基本戦略3] 産業・地域づくり](img/strategy3-ttl.gif)
新幹線開業効果を地場産業の振興につなげるには、首都圏という巨大な市場を取り込むとともに、産業経済面での結びつきを深めることで産業集積の高度化を図り、地域経済の競争力を強化することが重要です。
農林水産業では、ビジターに地元で旬の地場ものを味わっていただくこと、また、食材の質にこだわる消費者をターゲットにした食材の販路拡大を促進し、併せて、こうした取組みを通じブランド化を進めます。
地域づくりでは、地域住民の主体的な取組みとその効果が地域に還元される仕組みづくりという視点が重要です。地域づくり活動の核となる人材の育成を図るとともに、行政や企業、大学等との連携により、地域固有の資源を活用した新たなビジネスの創出に向けた取組みを促進します。
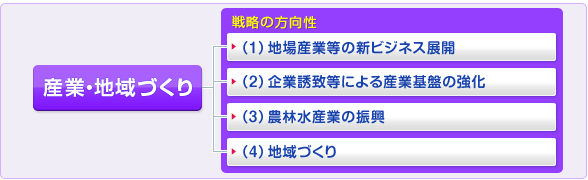
首都圏という巨大マーケットへのアクセス向上というビジネスチャンスを地場産業・伝統産業の振興に活かしていくには、新たな商品開発や販路拡大等に積極的に取り組むとともに、研究・技術面での人的交流の拡大を通じ、研究開発力の充実を図る必要があります。また、ビジターのニーズや期待にもしっかり応える地域商業の形成を目指します。
産業化資源を活用した新商品の開発・販路開拓への取組みの支援
農林水産業者と食品加工業者等が連携した商品開発や販路開拓に関する取組みの支援

県外発注企業と県内受注企業のマッチングのため受注開拓懇談会の開催(首都圏等での受注開拓懇談会や首都圏企業等の招へいによる企業交流懇談会の開催)
北陸新幹線の車輌での伝統的工芸品の活用に向けた取組みの推進
分野別のマッチング研究会(アグリビジネス、ITビジネス)の開催
予防と健康に関する世界的なライフサイエンス研究開発拠点の形成を目指す「ほくりく健康創造クラスター」構想の推進
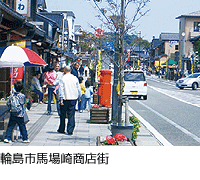
商店街のイベント、空き店舗対策、マーケティング調査等に対する助成
※1 いしかわ産業化資源活用推進ファンド(規模200億円、期間10年)とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構の地域中小企業応援ファンド事業を活用するとともに、株式会社北國銀行の協力を得て、官民共同でファンドを財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)に創設したもの。このファンドの運用益により、豊かな農林水産物、伝統工芸品、観光資源及び本県に集積するモノづくり産業やサービス産業を支える特有の技術といった本県の多様な強み(産業化資源)を活かした[1]産業化資源活用、[2]農商工連携、[3]医商工連携による新ビジネス・産業の創出を重点支援
新幹線開業により、企業活動の面では研究者・技術者等の人材の円滑な移動が可能になることから、本県のモノづくり産業クラスターの強化・拡充や情報・サービス産業の集積につながる戦略的な企業誘致を進めるほか、これらの企業を支える人材の招へい等にも積極的に取り組みます。

モノづくり産業クラスターの強化・拡充につながる企業やニッチトップ企業※1への成長が期待される企業等の誘致
優れた技術シーズを有する革新的ベンチャー企業への支援チームによる集中支援
本県企業の研究開発向上、モノづくり基盤技術の高度化の支援

首都圏等における相談窓口の設置、求人・求職情報の提供
※1 ニッチトップ企業とは、特定分野の市場におけるシェアトップ企業
※2 次世代型企業とは、高い技術力や独自の技術、ノウハウ等を有し飛躍的な成長が見込まれるもの又は相当の事業規模を有し、持続的な成長が見込まれるもの。概ね次の3類型に該当するもの。
→ 特定分野の市場でシェアトップになるような企業、新しい産業分野やビジネス形態で全国的なモデルとなるような企業、株式上場の可能性を有する企業
加賀、能登、金沢の山海の豊富な食材、独自の食文化はビジターを引きつける魅力を備えています。ビジターに対し地場ものを地元で味わっていただく取組みなどを通じ地産地消を進めるとともに、食材の安全安心とクオリティ(質)にこだわる首都圏の消費者をターゲットにした販路拡大を進めます。併せて、こうした取組みを通じ石川のブランドを浸透させていきます。
いしかわ「旬の地場もの」もてなし運動の推進
農商工連携の支援、ふるさと認証食品※1(かぶら寿し、かきもち、いしる等)の普及拡大

地産地消推進の一環として、県内飲食店、宿泊施設で県産食材を使用したメニューを提供いただき、県内外の方々に県産食材「地場もの」を知っていただこうという取組み

ブランド化を牽引する戦略作物の普及拡大
代表的水産物等の首都圏等への試験出荷やPR活動への支援(加能ガニなど)
首都圏での求評懇談会や実需者との交流会の実施
※1 ふるさと認証食品とは、石川県産の農林水産物を主な原材料として製造された加工食品や石川県に古くから伝わる伝統技法で製造された加工食品で、県がその品質や表示について一定基準に適合していることを認証している食品
民間事業者、地域づくり団体、行政等が連携する、例えば奥能登ウェルカムプロジェクトの「能登丼」のような地域住民が自ら企画する取組みを拡げていくことが大事であり、そのためには、従来の行政主導型から地元の内発的な取組み(企画、運営、情報発信等)に対し支援していく仕組みづくりが重要です。

奥能登ウェルカムプロジェクトの推進(能登丼のPR、能登回廊100選を活用した情報発信、米国の中学生等を対象とした日本文化や伝統芸能体験ツアーの受入れ)
ビジネスの手法を活用しながら地域の課題を解決するコミュニティビジネスの起業・運営等への支援
地域住民と連携した学生の地域貢献活動の促進
豊富な地域資源を活用した農業関連ビジネスの起業化支援
インターネットでの空き家情報をはじめ定住等に必要な周辺情報の提供
地域が主体となって、移住・交流居住に関する情報発信と移住者等の受入れに積極的に取り組む民間主導の組織づくり活動への支援
地域づくり協会や大学コンソーシアム石川※1等と連携して地域づくりに取り組むリーダーやコーディネーター役を担う人材の育成(いしかわ地域づくり塾等の実施)
※1 大学コンソーシアム石川とは、県内の全ての高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校)が連携して、教育交流・情報発信・調査研究等を行い、高等教育の充実・発展及び地域社会の学術・文化・産業の発展に寄与することを目的として、平成18年4月1日に設立されたもの。