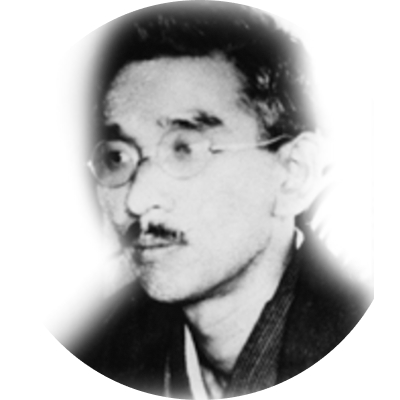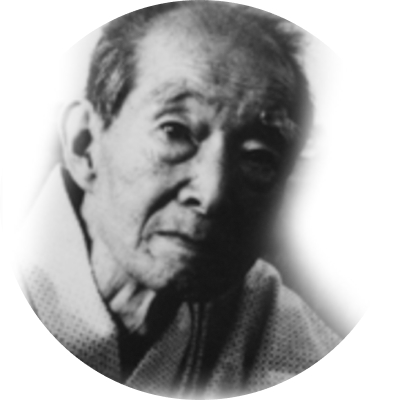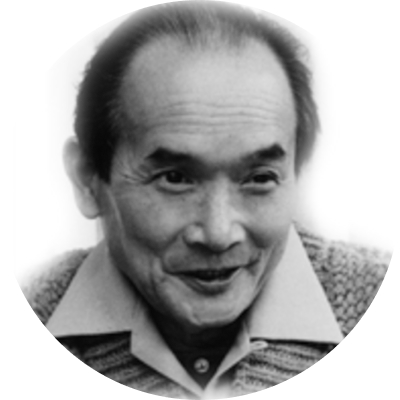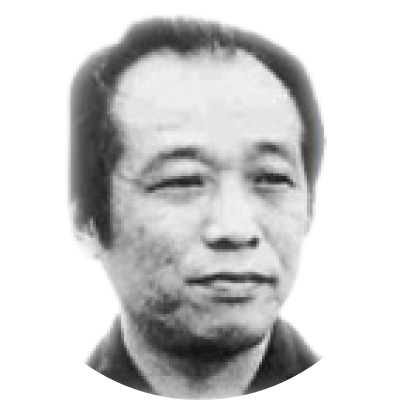松瀬 青々(まつせ せいせい)
明治2年~昭和12年(1869~1937)
俳人。本名松瀬弥三郎。大阪府生まれ。父は石川県羽咋郡出身、舟場で薪炭商加賀屋を営む。第一銀行に入社後、国学と和歌を学び、やがて俳句の道に入る。高浜虚子のすすめで上京し「ホトトギス」の編集員となる。
帰阪後、大阪朝日新聞社に入社。『宝船』(後、「倦鳥」と改題)を創刊(明治34年)、主宰し、関西俳壇に重きをなす。能登を故郷として愛した。『妻木』『鳥の巣』『松笛』などの句集のほか、俳話集『倦鳥巻頭言集』などがある。大阪に「倦鳥文庫」がある。