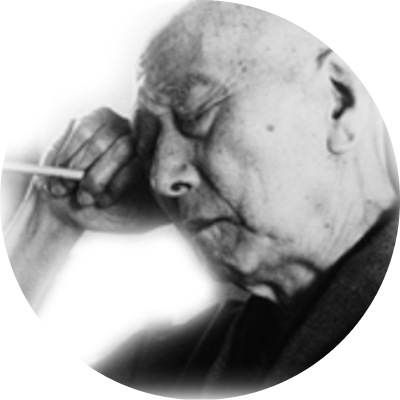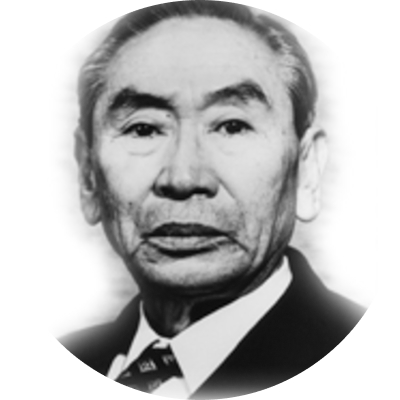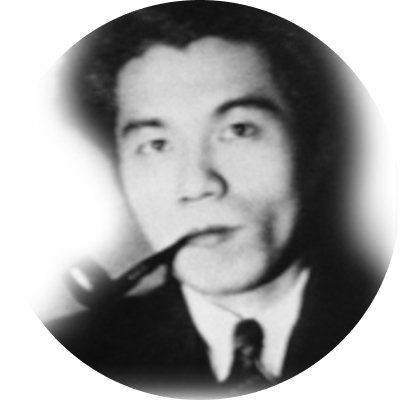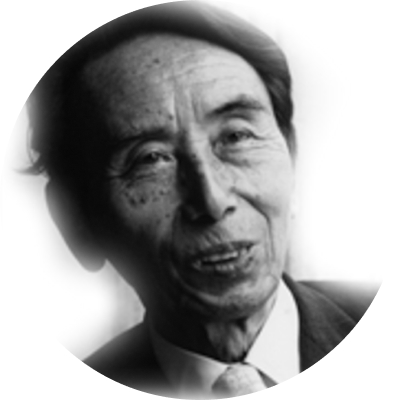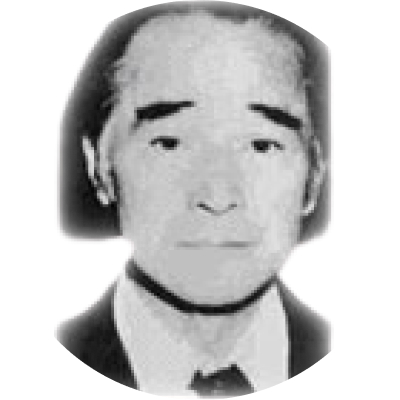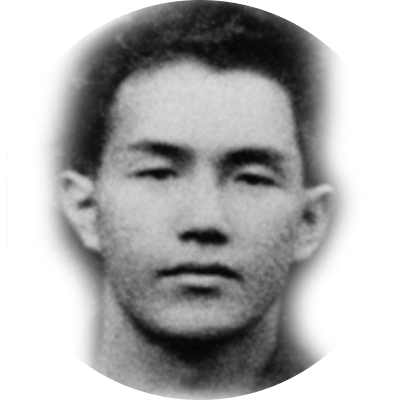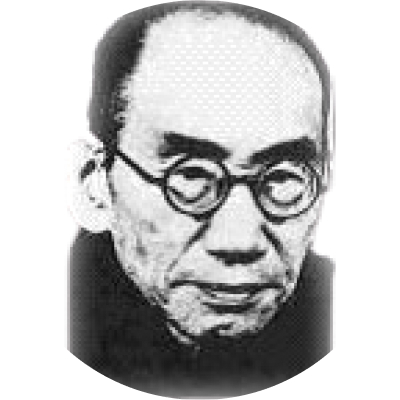
西田 幾多郎(にしだ きたろう)
明治3年~昭和20年(1870~1945)
哲学者。石川県宇ノ気町生まれ。東大哲学科選科卒。四高、学習院教授を経て京大教授、文学博士。四高在職中、三々塾を作り、学生と思索の場を持つ。
『善の研究』(明治44年)で思想界に登場、西洋哲学の手法を摂取しつつ東洋の思想伝統を表現すべく、独自の概念と論理の構築に務め、独創的な哲学体系を樹立。西田哲学を慕って俊才が集まり、京都学派を形成、日本思想界の指導的役割を果たす。文化勲章受章。著書は、『西田幾多郎全集』にまとめられる。