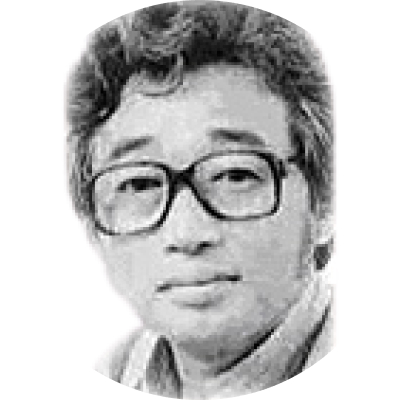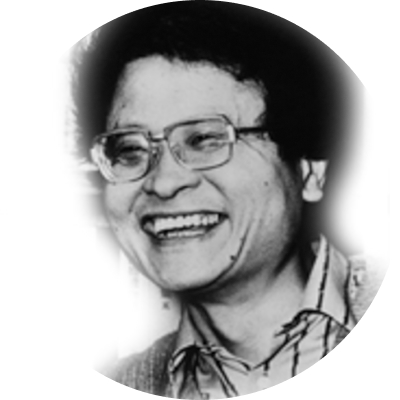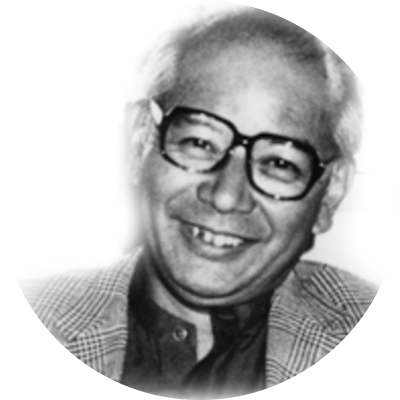
加賀 乙彦 (かが おとひこ)
昭和4年~ (1929~)
小説家、精神科医。本名
小木貞孝。東京都生まれ。室生犀星の遠縁にあたる。東大医学部卒。パリ留学から帰国後小説を手がけ、『フランドルの冬』を刊行(昭和42年、芸術選奨新人賞)、東京医科歯科大、上智大教授のかたわら『帰らざる夏』(昭和48年、谷崎潤一郎賞)、『宣告』(昭和54年日本文学大賞)などを刊行。作家生活に入り『湿原』(昭和60年、大佛次郎賞)、自伝小説三部作『岐路』(昭和63年)、『小暗い森』(平成3年)、
『炎都』(平成8年)などを刊行し、重厚な長編作家として知られる。