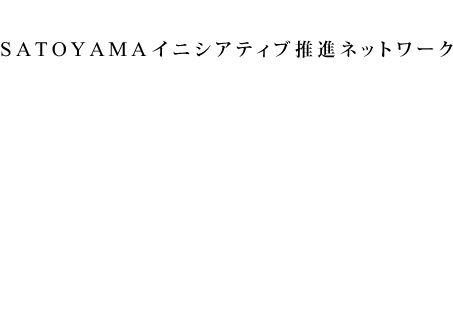
2月26日、SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワークの会員セミナー及び第1回実務者連絡会議を開催しました。
全国から約30団体・50名が参加し、会員同士の交流や意見交換など交流を図りました。
<SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク会員セミナー>
日 時 : 平成26年2月26日(水) 13:30 〜 15:00
場 所 : TKP大手町カンファレンスセンター16B (東京都千代田区)
内 容 : ≪基調講演≫
「自然を守れば自然が守ってくれる」
涌井 史郎 氏 国連生物多様性の10年日本委員会委員長代理、
東京都市大学教授、岐阜県立森林文化アカデミー学長
≪情報提供≫
島田 憲次 氏 環境省自然環境局自然環境計画課里地里山保全専門官
基調講演では、涌井氏から、「日本人は厳しくも豊かで個性的な自然に寄り添い、その特性を見極めるために様々なノウハウ、知恵を構築してきた。この「いなし」の智恵は、日本の農業土木、河川などさまざまな技術に投影されている。いなしの技術の根幹をなし、人間が生態系サービスを最大化して、自然の応力を最小化するための防波堤として作ったのが里山だった。」「里山は多面的効用を有し、地域におけるエネルギーと食料、水、そして自然災害の防止など、人が自然に深く関わり、手を入れることによって、暮らしを支える恵みを最大限に享受することができる自立循環型のシステムである。」と里山の重要性についてお話頂きました。
その上で、「人と自然の共生を実現した里山社会、そういうモデルをどのように構築をし、生態系ネットワークの形成、自然の恵みあるいは驚異にどのように対応するのか、地域の風土・文化・歴史、地域特性をどのように保全していくのか、それらを地域全体が課題として捉え、考えていくことが、生物多様性のみならず、その地域にとって極めて大きな、潜在的な活力に繋がっていく」とのメッセージを頂きました。

続いて、環境省自然環境局自然環境計画課里地里山保全専門官の島田憲次氏から里地里山施策に関する動向について情報提供を頂きました。
島田氏からは、地域による自律的な里地里山の保全再生活動の拡大や質的な向上を目指し、これまで情報発信・技術支援、各種手法の検討に取り組んできた旨の報告とともに、今後の里地里山の保全活用の方向性として、「森・里・川・海のつながり」を確保した生態系ネットワークの構築を図るべく、生物多様性保全上重要な里地里山の選定や保全活用策の検討などを進めていく旨の説明を頂きました。
また、支援策として「先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業」や「森林・山村多面的機能発揮対策」などについて紹介がありました。

会員セミナーに続き、参加団体による第1回実務者連絡会議を開催し、各団体の取組紹介や来年度事業方針等について意見交換を行ないました。
≪出席団体≫
【企 業】 アサヒビール株式会社、株式会社伊藤園、積水樹脂株式会社、大成建設株式会社、中越パルプ工業株式会社
【研究機関】 高等教育コンソーシアム信州、公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)、横浜国立大学
【NPO等】 特定非営利活動法人アースデイ・エブリデイ、環境ふくい推進協議会、認定特定非営利活動法人共存の森ネットワーク、
特定非営利活動法人鴻巣こうのとりを育む会、国際自然保護連合日本委員会、国連生物多様性の10年日本委員会、
公益財団法人埼玉県生態系保護協会大宮支部、三方五湖自然再生協議会
【行 政】 環境省、農林水産省、神奈川県、岐阜県、埼玉県、徳島県、栃木県、長野県、金沢市
【オブザーバー】 SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)事務局
事務局:石川県、福井県
